
2025/10/21
【後編】「ファン」はブランドをドライブする!戦略的思考で築く「健全な関係」
なかじま
前編では、ブランドを成功に導くための「戦略」の基本構造と「7つの問い」についてお伺いしました。後編では、その戦略的思考を、ブランドをドライブする重要な要素である「ファン」との関係構築にどう活かすかに迫ります。ファンとは単なる顧客以上の存在。その心の動きを捉え、ブランド価値を高めるための具体的なアプローチと、工藤拓真氏が考えるファンとの「健全な関係」について深掘りします。

工藤 拓真ブランディング・ディレクター/ クリエイティブ・ディレクター ㈱dof執行役員/㈱BRANDFARM代表/ 株式会社YAMAP社外取締役/ 多摩美術大学統合デザイン学科講師他
電通を経て、ブランディングを起点に、事業開発、商品開発、広告制作等のディレクションに従事。資生堂マキアージュやUNIQLOスポーツなどのリブランディング。TAXI GOや伊藤忠商事などのコミュニケーション戦略。NewsPicksやTOYOTAなどの新事業開発。サントリーや三菱鉛筆uniballなどの商品開発。タクシー番組『ひみつのプライム』やTokyo Motor Show2017などの番組企画ディレクションと、幅広く活躍。自著に『進撃の相談室ー 13歳からの「戦略論」(講談社)』など。
目次
Plan/f
前編でお話いただいた「7つの問い」は、ブランド戦略の根幹をなすものとして非常に参考になりました。ここからは、その戦略的思考を「ファン」との関係にどう活かすかというテーマでお伺いしたいと思います。工藤さんは、ブランド戦略の中でファンをどう捉え、どう関わっていくべきだとお考えですか?
工藤 拓真さん(以下・工藤さん)
ファンマーケティングやブランディングにおけるファンとの関わりについてご相談を受ける際、まず私がお伺いするのは「ファンの定義って何なんですか?」という問いです。ブランディングと同様に、ファンマーケティングもその定義が人によってバラバラになりがちです。「ファンを増やしたい」という話が、結果的に「新規顧客を増やしたい」という話にすり替わってしまうケースも少なくありません。
また、ファンとの関係は、売上と直接結びつかないこともあります。その結果、ファンとのコミュニケーションが単なる「楽しい交流」で終わってしまい、ビジネスとしての成果に繋がらないこともあります。
先にも言いましたが、私個人の定義としては、ブランディングとは「記憶の箱を創る活動」だと考えています。その「記憶の箱」がポジティブな形で積み重なり、「健全な関係の中で、ちゃんとお支払いし続けたい」と思えるような関係性のことだと考えています。

Plan/f
「健全な関係の中でお支払いし続けたい」という定義は非常に腑に落ちます。では、具体的にファンとの接点を作り、そうした関係を構築するためには、どのようなアプローチが有効でしょうか? 具体的な事例などがあれば教えてください。
工藤さん
具体的な事例としては、登山アプリの「YAMAP(ヤマップ)」がありますね。登山という限定的なコミュニティの中で、ユーザーの皆さんがYAMAPで活動すること自体が、山に対する義務のようになっているんです。「ここ危険」「ここ楽しい」といった情報共有や日記投稿機能を通じて、ユーザー同士が価値を創造し、それがまた新たなユーザーのモチベーションにもつながっています。YAMAPは、ファンの持つ言葉の温かさを結果に結びつけ、コミュニティ全体でブランドを成長させている例だと思います。
Plan/f
YAMAPのような好事例がある一方で、ファンとの接点施策を行う上では、どのような点に注意すべきでしょうか?
工藤さん
ただ、ファンミーティングやリアルイベントなど、ファンとの接点施策を行う企業は多いですが、「なんとなく楽しくやろう」で終わってしまっては意味がありません。なぜなら、ファンとの関係は、実は非常にシビアな「戦い」だからです。ブランドを最もドライブさせる「道具」であり、一番「稼ぐ」ための行いだと捉えるべきでしょう。
既存のファンは、既にブランドに対して良い感情や「貯金」を持っています。ファンイベントは、その「貯金」を使うだけでなく、さらに「もっと好きになってもらう」ための場であるべきです。
そのためには、前編でお話した「7つの問い」が重要です。「今いるファンがどういう状態にあるのか、どういう声を持っているのか」を正確につかみ、彼らが「もっと良いお金の使い方をしたい」と思えるような「幸せ」を提供できるかを真剣に考える必要があります。
Plan/f
ファンとの関係を「稼ぐ」ための行いと捉える上で、具体的にブランド側が提供すべき価値や、意識すべき視点はどのようなものでしょうか?
工藤さん
ファンが「もっと語りたくなる、発信したくなる」場を作ることは重要です。しかし、これは安易に「良いことだけを言ってもらう」ように仕向けるのは危険です。なぜなら、不自然な言動はすぐに消費者に気づかれ、「何か裏があるのでは」という不信感につながるからです。語ってほしい内容をコントロールするのではなく、ファンが「自然に語りたくなる」ような本質的な価値を提供し、共感を醸成することが重要です。
Plan/f
ファンとの関係構築は、非常に深い戦略と思慮が必要なのですね。最後に、マーケティング・ブランディング担当者へメッセージをお願いします。
工藤さん
ファンとの関係は「無邪気に楽しむ」だけでなく、ブランドを成長させるための「シビアな戦い」だと認識することが何よりも重要です。しかし、この「シビアさ」と真摯に向き合うことで、ブランドは大きくドライブします。
「7つの問い」のような戦略の基本構造を、ファンとの関係構築にも適用し、彼らが「もっとこのブランドで幸せになりたい」と思えるような価値を創造し続けること。それが、これからの時代に求められるファンとの新しい関係構築の形だと思います。

Plan/f
最後に、工藤さんがリアルな消費者として「これは自分はファンだ」と言えるようなモノコトがあれば教えてください。
工藤さん
3周回って『ユニクロってやっぱすごいんだな』と感じています。アイテムにもよりますが、特にエアリズムの下着なんかは、どんなハイブランドやアフォーダブルな素材よりも、機能面で圧倒しているなと感じます。それがブランドになっている、と思いますね。
単に機能面だけでなく、アパレルのプロフェッショナルたちが『ここまでやるのか』と驚くような、縫製や工夫のこだわりを見ると、『狂ったようにやり続けた結果、ここまで到達するんだ』と感じます。
―工藤さん、貴重なお話をありがとうございました!
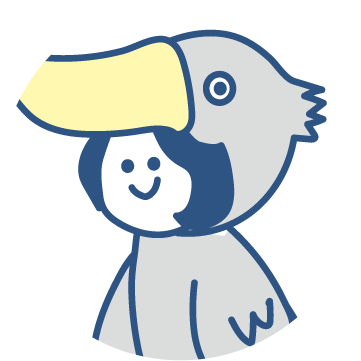
編集者なかじま
「無邪気な楽しさ」の裏にある「シビアな戦い」
工藤さんの言葉を胸に、私たちもブランドとファンとの関係性に真摯に向き合い、お客様がその覚悟を持てるよう、共に伴走していきます。
![]() 注目のキーワード
注目のキーワード
![]() 人気の記事
人気の記事