
2025/07/01
【後編】「好き」と「ファン」の違い―「好き」が継続するヒントとは
たにぐち
前編では、「好き」を言語化することが自分自身の理解を深めることにつながる、というお話を伺いました。後編では、「好きであること」と「ファンであること」の違いに焦点を当て、「好き」から「ファン」へと気持ちが深まっていく過程で、発信側にできることについて考えていきます。

三宅香帆文芸評論家・京都市立芸術大学非常勤講師
1994年高知県生まれ。京都大学大学院博士前期課程修了。株式会社リクルートに入社後、2022年に独立。主に文芸評論、社会批評などの分野で幅広く活動。著作には『人生を狂わす名著50』(ライツ社)、『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』(集英社新書)、『「好き」を言語化する技術』(ディスカヴァー携書)など多数。
三宅 香帆さん(以下・三宅さん)
私は、「好きであること」と「ファンであること」は、まったく別物だと思っています。「好き」は自分の心が動いたときに、気軽に口にできるものです。一方で、「ファン」はその対象が自分のアイデンティティの一部になるような、より深い関わりを持つ存在だと考えています。
三宅さん
「継続性」が大切だと思います。ファンマーケティングの観点では、企業や推しが好きだと思ってくれる人たちの気持ちを、いかに継続させるかが重要です。例えば、「この本が好き」と思っても、すぐに「この本のファンです」とはならないものです。しかし、ある作家の本を読み続けたり、シリーズを追いかけたりするうちに、「この作家のファン」「このシリーズのファン」と気持ちが深まっていきます。ファンとは、「好き」という気持ちが継続することで生まれるのだと思います。

三宅さん
一番多いのは「裏側」だと思います。例えば、アパレルブランドが洋服を作る過程や、携わっているスタッフについてSNSで発信している例があります。完成した商品だけでなく、その制作過程も含めて情報を楽しめるのは、ファンにとって嬉しいことです。よりその世界に入り込みたくなるような魅力があります。
三宅さん
そうですね。普段は見えない部分に触れられることはもちろんですが、もう一つ大切なのは、そうした発信が継続的に行われていることだと思います。「裏側」は常に存在していますし、それらを継続してファンに届けていくことが重要です。人間関係でも、たった一度の飲み会よりも、毎週ランチを共にする方が自然と仲良くなります。それと同じように、キャンペーンを一度や二度実施するだけでなく、日常的に楽しみにできる出来事があることで、「好き」という気持ちはさらに大きくなっていくのだと思います。
三宅さん
「好き」と「ファン」、「推し」の違いには、「応援したくなる」という気持ちが関係しているのではないでしょうか。例えば、ある企業が商品を購入すると、その売上の一部が寄付として桜の保善活動につながるというキャンペーンを行っていました。このキャンペーンは、商品を購入するという行動が桜の保善活動への「応援」になり、その先のゴールが分かりやすくなっている事例です。自分の「好き」から生まれた応援がどこに届いているのかをイメージできることも、「好き」という気持ちを継続してもらうための重要なポイントだと思います。
三宅さん
人は、他人が好きなものを自分も好きになりやすい傾向があると感じます。ファンの方々が発する言葉から影響を受けることもありますし、同じ「好き」を持つ者同士でのコミュニケーションを楽しいと感じる人も多いと思います。
三宅さん
何かの「ファン」や「推し活」をしている方は、やはりSNSなどでその気持ちを発信したくなるものです。ただ、誰もが積極的に発信できるわけではないので、SNSで投稿しやすい環境を整える工夫が必要だと感じます。例えば、ビジュアルで分かりやすい画像があることで投稿のハードルが下がりますし、画像付きの投稿は「この人は〇〇が好きなのだな」と一目で伝わるため、同じ「好き」を持つ人同士がつながりやすくなります。

三宅さん
著書でも書きましたが、「好き」という感情は「共感」か「驚き」のいずれかがきっかけになると思っています。自分の過去の経験と共鳴するものや、今まで知らなかった発見がポジティブな感情として訪れる時、「好き」が生まれるのではないでしょうか。
やはり本を読むことが好きです。一人で本の世界に浸る時間が一番心地良いですね。本を通して他者の考え方や物の見方に触れることができ、気兼ねなく自分だけの時間を過ごせるところが私にとっての魅力です。
―三宅さん、ありがとうございました。
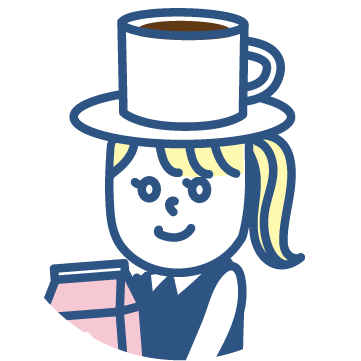
編集者たにぐち
”「好き」は、「共感」か「驚き」のいずれかがきっかけになる”と三宅さんにお話いただいた時、より一層「好き」を言葉で残しておきたいと思いました。共感は経験が増えるほど深まるし、驚きは新しい発見をするたびに変わっていく。「好き」は、その時にしか感じられない特別な感情なんだなぁと改めて気づきました。
![]() 注目のキーワード
注目のキーワード
![]() 人気の記事
人気の記事