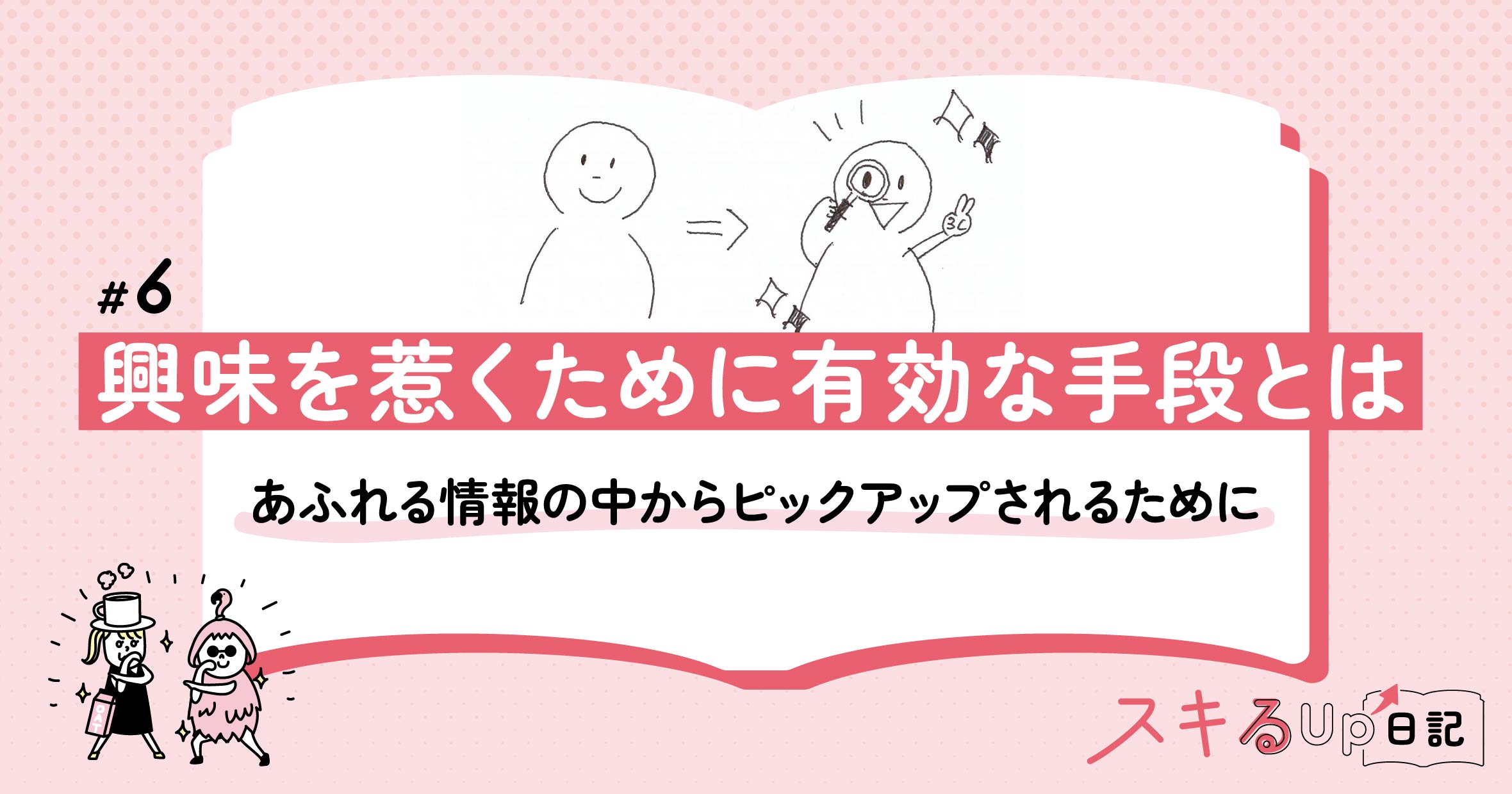
2025/02/04
興味を惹くために有効な手段とは―あふれる情報の中からピックアップされるために
たにぐち
スキるUP日記#2にて、
私が考える“スキ度があがる3つのポイント”についてお話させていただきました。
しかし、記事を再読すると、
そもそもスキになる前段階の“興味を持ってもらう”までの難易度が
すごく高いのではないかという新たな課題が発生。
みなさまも、「商品名は知っているけど、どんな商品かわからない」とか、
逆に「どんな商品かわかるけど、商品名がわからない」といったことはないでしょうか?
今回は、たくさんの情報があふれる今の時代に、
なんとなく知っている→興味を持ってもらうためのきっかけづくりや
有効な情報の伝え方はないか考えて行きたいと思います。
ここでいつもの自分の経験の深掘りをしていきたいと思います。
私は昨年ビールがおいしく飲めるようになったこともあり、
ビール売場に立ち寄る頻度が高くなりました。
今までビール売場を何度も見ていたはずなのに、「ビールを買おう」という気持ちで見ると
その種類の多さと売場の広さに驚愕したのを覚えています。
ただ、毎回「ビールを買う」ことが目的だったので、
とくにこだわりなく選択をしていました。
そんな中、研修先であるビールブランドA社の社員さんと知り合ったことで、
今まで何十回も見てきたA社のCMが目に入るようになり、SNSを覗くようになりました。
また、たくさんの種類があるビール棚から「これ!」と
A社のビールを名指しで選ぶようになるなど、私の行動が変化しました。
この経験は今回のテーマである、
なんとなく知っている→興味を持つことにステップアップした事例なのかなと思います。
では、私はこれまでA社の情報に何度も接触してきたはずなのに、
なぜ、興味を持てるようになったのでしょうか。
それは、“興味がある人からの直接的な情報の受け渡し”なのではないかと私は思います。
「興味がある人」とは、私にとって身近だったり共感する部分が多い人を指しており、
そういった人の情報は私の興味を惹きやすいのではないかと思います。
ふり返るとA社の社員さんは同世代で話しやすく、
初対面なのに「私、この人すきだわ~。仲良くなりたい」と思うほど、
私にとって「興味がある人」だったんですよね。
なので、会話の中でサラッとお話されたA社のテーマがすぐ頭の中に記憶され、
A社のビールを選ぶ理由が私の中にできたのではないかと思います。
この行動変化は、前回インタビューをさせていただいた箕面ビールさんに対しても同じように起きています。箕面ビールさんのビール造りへの姿勢や想いを直接聞き、私の中で共感・支持したいという存在になったため、その後、箕面ビールさんの情報を自分から取りに行くようになったのではないかと思います。
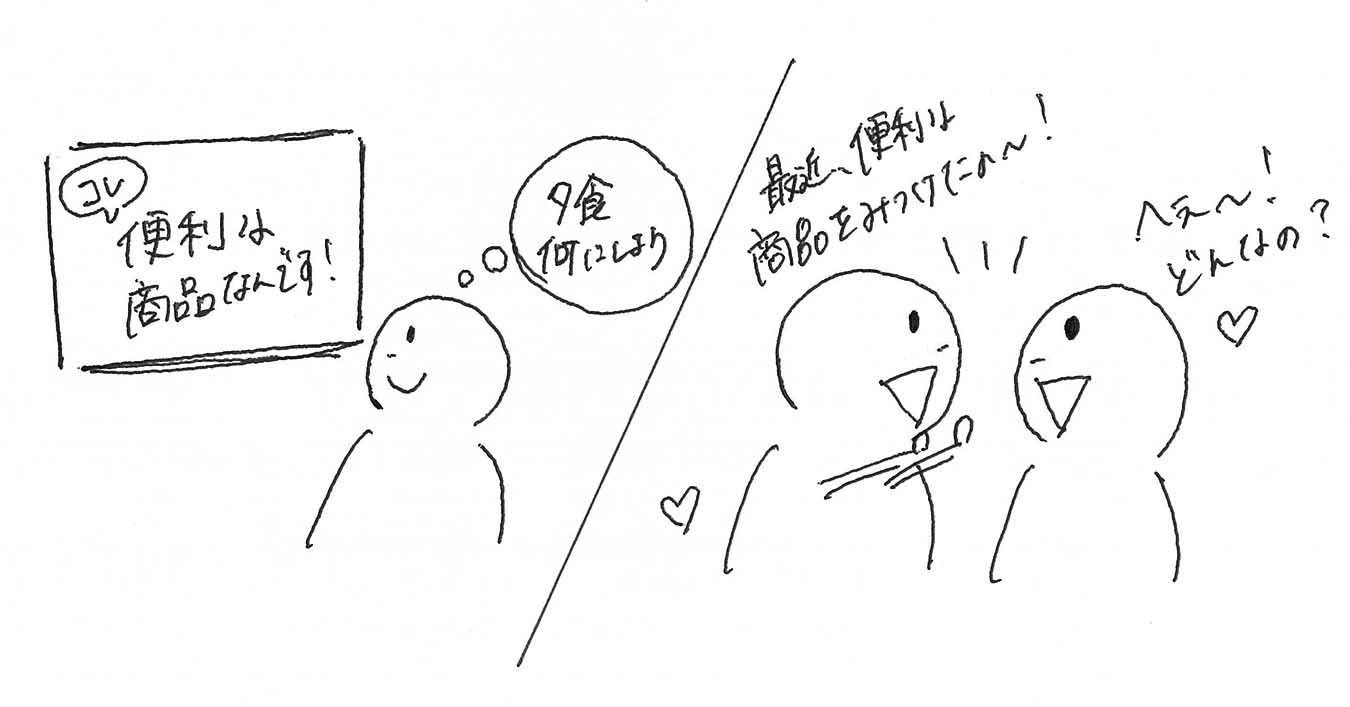
今回の気づきは、以下の3つです。
“情報発信先が誰でもいい”ということではなく、
自分の好きな人、自分にとって興味がある人からの直接的な情報の受け渡しが、
「知っている」→「スキ」の間にある、「興味を持つ」という大きな壁を乗り超えるための
有効な手段だと私は思いました。
となると、このような消費者の行動変化をブランド側が起こしたいと思った時にできることは、既にブランドを好きな人(興味がある人)のスキ度をさらに高め、その人にとって、自分の周りにおすすめしたい存在になることではないでしょうか。
みなさまの「知っている」→「スキ」へと変化した経験、その変化の要因は何かなど、
ぜひ、お聞かせください!
問い合わせフォームからのご連絡お待ちしております~♪
\ファンと向き合う一歩目を、Plan/fといっしょに/
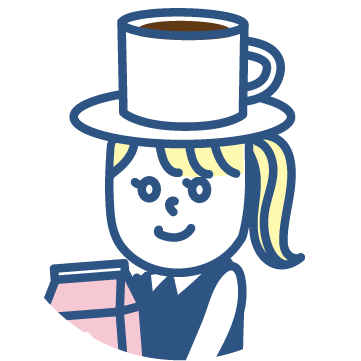
編集者たにぐち
「目を引く」ではなく、次のアクションにつながる「興味を惹く」への難易度の高さや、日々、無意識に情報を取捨選択していることに改めて気づくことができました!
![]() 注目のキーワード
注目のキーワード
![]() 人気の記事
人気の記事